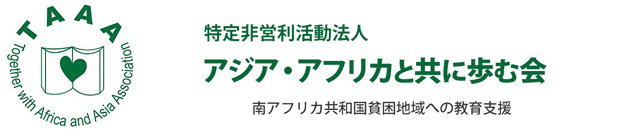南アニュース・IZINDABA IZINDABA 第11号 2006年4月8日
南ア映画"TSOTSI(ツォツィ)"と"YESTERDAY"を見て
南アフリカ映画"TSOTSI(ツォツィ)"が、本年度アカデミー賞外国語映画賞を受賞しました。 昨年の"YESTERDAY"のノミネートに続く快挙です。TSOTSIとは、タウンシップのスラングでギャングを意味します。授賞式には主演俳優、ディレクターなどが列席していましたが、もう1人、南アのベノニ出身の女優シャーリーズ・セロンも主演女優賞にノミネートされていたため、南アのメディアは大騒ぎでした。(彼女は昨年主演女優賞を受賞しています)
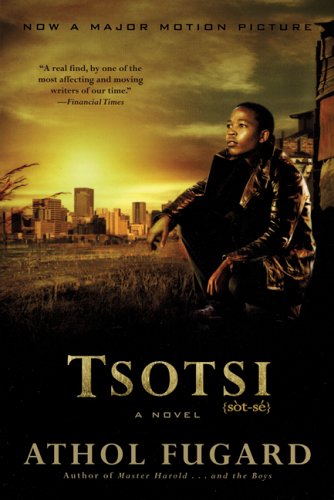
http://www.tsotsi.com/english/index.php
TSOTSIの制作者、ディレクターなど主要なスタッフは白人ですが、俳優はもちろん、裏方にも大勢の黒人スタッフが参加しています。こちらでは、音楽をはじめとしてエンターテイメント産業が急成長しています。この映画の中で使われている音楽はKWAITOというジャンルで、南アのタウンシップ版ヒップホップです。アメリカでもヒップホップのミュージシャンが映画に出演していますが、TSOTSIにもKWAITOのスター、ZOLAがギャング役で登場します。この映画、とにかく今の南アの姿を如実に描いています。南アをよく知る人たちにとっては、一シーン、一シーンが目にしたことや、聞いたことがあるものではないかと思います。もちろん、これは世界中の都市の周辺にあるスラムで抱えている問題を描いているといえます。極度の貧困の中で、愛情も安らぎも受けずに育ち、暴力と隣りあわせで生きる若者たちは、どうやって他人の、そして自分自身のヒューマニティーを見出すことができるというのでしょうか。
主人公はストリートチルドレン上がりの冷血ギャング。でも、いつも何かを考えているような、さびしそうな表情が印象的です。私がジョハネスバーグでボランティアをしていた"ストリートワイズ"というシェルターに、プリンスというキュートでとても繊細な少年がいました。彼はソウェトの出身で、両親は健在でしたが、アル中のため子供の養育ができず、おばあさんに育てられていました。しかし様々な理由でそこにもいられなくなり、友達とヒルブロウのストリートで生活するようになりました。その後、ストリートワイズのソーシャルワーカーに出会い、シェルターで生活を始め、学校にも通えるようになったのです。彼は絵が大変上手で、歌や踊りも抜群のアーティストでした。ストリートワイズが閉鎖されてから、他のシェルターに移ったと聞いていましたが、ここ数年会っていません。映画の主人公とちょうど同じくらいの年齢で、ルックスもどことなく似ていたので、彼のことをふと思い出してしまいました。
郊外の豪邸の門の前で主人公がカーハイジャックする高級車に乗っているのは白人ではなく、彼と同じ黒人です。南アでは黒人層の中での経済格差が年々大きくなり、犯罪も、"貧しい黒人が豊かな白人を襲う"、といった単純な構造ではなくなってきています。もちろん、黒人層が経済界に参入していくことは重要ですし、資本主義経済の下、競争、格差が生まれるのは当然かもしれません。また、いわゆる"黒人中産階級"が市場における購買力をアップさせているともいえます。南アフリカ経済は、通貨ランドも強く、株価も最高値を更新し続けるといった、空前の景気に沸いています。しかし一方で、水道も電気もないトタン屋根のシャックに住み、一日数10ランド(1ランド約20円)で重労働をさせられたり、それでも仕事があればいい方で、国が変わってからずっと失業者でいる人たちがこれほどいたりするのは何故なのでしょうか。アパルトヘイト以後の民主国家南アフリカが目指していたのはこのような社会だったのでしょうか。
話がそれましたが、映画のストーリーの中心は、ひょんなことから赤ん坊を育てなければならなくなってしまった主人公が、自分の過去を思い出しながら次第に人間性に目覚めていくというものです。TSOTSIを作り出してしまうような家庭の環境、そのような家庭を作り出してしまう社会を描いています。この映画のユニークなところは、ものすごく厳しく、つらい現実を描いていながら、思わず笑ってしまう場面が多いことです。ギャングの面々も何だか憎めないところがあって、やることもズッコケていて思わずふき出してしまいます。ただ、それが余計に悲しさを増すことになるのです。もし彼らがあたたかい家庭で、あらゆるチャンスに恵まれて育っていたら、どんな若者になっていたのだろうかと考えると心が痛みます。
先日、SABCでとても興味深い番組を放映していました。ケープタウンの郊外に住む白人のロックバンドのメンバーたちが、黒人居住区カエリチャのゴスペルグループと競演するというドキュメンタリーです。白人の青年たちは初めて黒人居住区に足を踏み入れ、その厳しい生活に驚きを隠せません。ゴスペルグループとはさすがにミュージシャン同士、あっという間にセッションが始まり、感動的な"ロックンゴスペル"が誕生します。白人の若者たちの1人が、"タウンシップの人たちはこんなに大変な暮らしをしているのに、何故みんなあんなににこやかで明るくいられるのですか"といっていたのが印象的でした。これは私もいつも感じていることで、今では、"それがアフリカ人"と思っています。
さて、もう一本の映画は、昨年のアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、惜しくも受賞を逃した映画"YESTERDAY"です。こちらは南アの地方の村が抱える問題をリアルに描いています。舞台はクワズールーナタール州の地方にあるズールー人の小さな村。村からクリニックまで歩いて2時間かかるのですが、具合の悪い主人公はミニバス代も惜しいので、小さな娘と歩いて向かいます。やっとたどり着くとそこは長蛇の列で、結局その日は診てもらえず、村に戻っていきます。最近村にやってきたばかりの学校の先生が、見るに見かねてミニバス代を出してくれて何とかクリニックに行き、ズールー語の堪能な白人女性のドクターに診てもらいます。血液検査の結果、HIVに感染していることを告げられるのですが、彼女にはそれがどういうことだかよくわかりません。ジョハネスバーグの金鉱で働く夫に連絡を取ろうとしてもつながらないため、意を決し、ジョハネスバーグへと向かいます。夫に会い、話をすると、夫は彼女を殴ります。やがて、具合の悪くなった夫が村に戻ってきます。小さな村の女性たちは、口々に噂話をし、彼女たちをあからさまに避けるようになっていきます。自分も身体の衰えと闘いながら、夫の世話をし、力強く生きていく主人公。クリニックでドクターに"あなたの身体は丈夫ね。そんなに悪くなっていないわよ"といわれ、"いいえ、身体じゃないんです。強いのはここ(と頭をさす)なんです。娘が学校に上がる姿を見るまでは、絶対に死ねません"という。彼女はどんな困難にあっても前向きに生きていく、たくましいアフリカ女性なのです。
YESTERDAYは主人公の女性の名前なのですが、演じているのは"サラフィナ"の舞台や映画でおなじみのレレティ・クマロさん。本当に味のある女優です。TSOTSIの主人公の親友で、小太りのギャングメンバーの1人は、どことなく若き日の西田敏行さんに似ていて、本当に憎めないギャング役でした。カーハイジャックに遭うファミリーの夫役は、こちらで一番人気のソープドラマ"GENERATIONS"の主人公を務める俳優で、彼は南アの若手男優の中で実力、人気ともトップといえます。ジョハネスバーグ駅の足の悪い路上生活者役はベテラン俳優で、鬼気迫るものがありました。準主人公の女優はすでにネルソンマンデラの自伝映画で娘役に決まったそうです。主人公の男優も、準主人公の女優も、今回の映画がデビュー作で、いきなりアカデミー賞を受賞してしまったということになります。改めて、南アには才能のある若者が多いことを感じました。
どちらの映画も、ぜひ日本で公開され、皆さんに見ていただきたいと思います。これまで南アが舞台の映画は、ほとんどアパルトヘイトに関係したものでした。そして今、アパルトヘイト後の南アがどのようになってきているのか、これらの映画は、まるでドキュメンタリーのように私たちに見せてくれるのです。