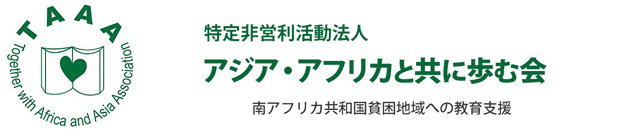南アニュース・IZINDABA IZINDABA 第14号 2007年4月28日
フリーダムデーに思う
4月27日は初の全人種による民主的な選挙が行われた日を記念し"フリーダムデー"の祝日となっている。1994年4月27日、私は当時ANC東京事務所代表であったジェリー・マツィーラ氏と東京の南ア大使館にいた。彼は大使館で在外者投票を行ったのだ。40代半ばにして初の一票を投じる彼の誇りと希望に満ちた姿が思い出される。あれから13年、南アは大きく変わった。マンデラ氏が大統領となり、ターボ・ンベキ氏が引き継いだ。マツィーラ氏はベルギー大使として活躍している。
"変わった"というより"普通の国になった"と言うべきかも知れない。民主的な選挙でリーダーを選び、人種に関係なく能力でポジションに就き、自らの意志で進む道を決定する選択肢を持つ、これらは当然のことである。政府や社会に対して不満があれば、それをはっきりと誰にも抑制されずに発言できる。デモなどの形で意思を表示することができる。これは民主的な国家として機能している証拠である。そして資本主義国家であれば当然競争社会となり、その結果として経済的な格差が生まれる。しかし、"普通の国になった"代償としてのこの経済格差は仕方ないのだろうか。
最近、一般の人々の政府への不満と不信が高まってきているように感じられる。北西州の町クツォンでは、27日"反フリーダムデー"のデモがあり、警察が出動して鎮圧したが、デモに参加した人は"アパルトヘイト政府がソウェトの若者たちに行ったことと同じことがここで起きている"と話した。この町はハウテン州から北西州に組み込まれ、それに不満を持つ住民がここ数ヶ月間デモやボイコットを続けている。学校長や教師も参加しているため、学校では授業にならずほとんど閉鎖状態だという。大都市から離れた州の境界線上にあるこのような町では失業率が圧倒的に高く、住宅、電気、水道などの整備も遅れている。また往々にして市長や役人たちが怠慢で、住民たちは10数年待ち続け、我慢してきたものが爆発しているかのように見える。
先日、南アフリカ航空(SAA)のトップが何千万円ものボーナスを受けていたという報告があった。SAAは半官半民で業績もいまひとつである。このような莫大な額は税金を使って払われていたのではないかと言われている。SAAのトップであれば、すでにどこに行くにもファーストクラス、一流ホテルにリムジンで送り迎えと最高級の待遇であろう。その上寛大なボーナスをもらってまさに"フリーダム"を満喫しているようだ。ケープタウンに降り立つとき、眼下に広がる居住区やスクウォッターを見て胸が痛まないのだろうか。それとも、これは成功した私の当然の権利と思っているのだろうか。
この"フリーダム"を勝ち取るために数多くの有名無名の人々が自分の地位も、富も、家族も、そして命までも投げうってこの国の人々のために闘った。それらの犠牲があって今があるのだ。ところが、最近ではあまりにも人々が自分のことばかり考えているような気がしてならない。スティーヴ・ビコが今の南アを見たら、こんなに貪欲で利己主義な人々のために自分は命を投げうって闘ったのか、と嘆くのではないだろうか。
クワズールーナタール州では警察官の夜勤手当がカットされるという発表に、警察官たちは"こうなったら公然と賄賂を受け取るしかない"と怒りを露わにしている。このコメントは行き過ぎかもしれないが、危険で大変な仕事である警察官の手当てをカットするのは不当ではないか。ここの所盛んに行われている道路名の変更などに予算を使わずに、警察官や教師への給料を上げるべきである。そうしなければ、優秀でやる気のある人々がどんどん職を離れていき、ますます治安の悪化や教育の質の低下につながるだろう。まず、一握りのトップに莫大な給料を払うようなことは、この国の今の時点では、間違っていると思う。
新しくエリートになった人々は我先に郊外の大きな家と高級車とブランドの服飾を買い漁る。"フリーダム"がもたらしたのはこのような競争社会なのだ。この貪欲な購買力によって大手メーカーは利潤を得るという仕組みだ。
国民がある程度平均的な暮らしをしている私たち日本人は、"お金や物質的な豊かさだけが幸福だとか人生のゴールではない"と言えるのであるが、発展途上にある国の人々にとってはやはりそれが目標であることは理解できる。しかし、国民の多くが老人年金に頼って生活をしている現実の中、ほんの一握りの人々が桁違いの給料をもらっているこの経済システムには疑問を感じる。まずは大多数の人々、特に若い世代が職に就けるための訓練や指導を行うために大きな予算を投じるべきである。そして、より多くの雇用を吸収できる産業を振興するべきだ。さもなければ近い将来、経済が行き詰ってしまうのではないだろうか。このような状況が続き、もし人々の怒りと我慢が限界となった時どうなるのだろう。早急に大規模な経済システムの改革を願う。
南アは世界一ともいえる素晴らしい憲法を持っている。ここではすべての人間の基本的な権利が守られている。人種、性別、宗教、言語など、あらゆる要因においてすべての国民は差別を受けてはならないと定義されている。とはいえ、イースターやクリスマスはキリスト教の祝日で、イスラム教やヒンズー教の祝日はない。また英語が圧倒的に優位にあり、職に就くためには英語が完璧であることは不可欠である。それらを一つ一つ取り上げては"権利"を主張して論争が起きる。
ところがもっとひどいのはこのような憲法の下で基本的な人権が全く守られていないケースだ。例えば、農場労働者は農場のオーナーが変わったとたん、長年住んできた農場内の小屋を何の告知も補償もなしに追い出される。先日は農場を野生動物公園にするため労働者の住む小屋の近くにバッファローを放ち、労働者が踏み殺されるという事件が起きた。基本的な人権に対して全く声を上げられない人々がどれだけ多いことか。彼らは"フリーダム"を享受するどころか未だ"フリーダム"を得ていないのである。
もちろん、政府への批判や絶望感だけでは前に進まない。人々が政府への信頼と未来への希望を失ったら国は漂流してしまう。私はこの国の、平和裏に奇跡的ともいえる変革を成し遂げた人々の、前向きなパワーと限りないエネルギーを信じている。特に"肌の色で住むところや学校が差別されていたなんて信じられなーい!"という若い世代に期待する。だから彼らに、私たち大人が暗く憂鬱な顔をして政府を批判する姿ばかり見せてはならない。大金持ちのエリートになることだけが成功だというような意識を植え付けてはならないのだ。
4月26日付のデイリーニュースでジャーナリストのマックス・デュプリーズ氏のフリーダムデーへのメッセージを紹介する。
<カラードの人々がかつては黒すぎて今では白すぎると嘆く。大多数の黒人の生活はアパルトヘイト当時と比べてほとんど変わっていないと主張する。白人は主流からはずされ、のけ者にされていると被害者意識丸出し。それぞれが犠牲者を名乗る国家になってしまったようだ。もちろん、政治家に対する不満や、役人、警察の怠慢に対して声を上げ、汚職や犯罪、人種差別などに対しては抗議をしていかなければならない。金持ちはケチで貧乏人は怠慢だと批判も必要だ。しかしそれぞれが文句ばかりで前向きな意識を失ってしまってはいないか。このような否定的な態度でこの国を見限るべきではない。
先ごろ白人の若者のロックバンド"フォクオフポリースカー"のメンバーからアフリカーンス語の新聞へのメッセージを読んだ。バンドのリーダー、ハンター・ケネディーは"ネルソンマンデラが大統領になったとき僕は12歳だった。そして今25歳、僕たちは100%罪責感なしの若者で、僕たちには様々な境界線は全く存在しない"と言う。"僕たちは真実と和解について歌っていきたい。寛容というダンスを踊りたい。僕らはすべてのものから自由なんだ。僕は貧乏で、僕は白人。それでいいじゃないか。今、僕らは「恐れ」という巨大な王国に対して最後の闘いを挑まなければならない"
この最後の言葉をTシャツにでもプリントして全国の若者に配りたいくらいだ。我々は他人への恐れ、未知のもの、未来、失敗、他人を信頼すること、不安、偏見への恐れに対して闘っていかなければならないのだ。>
結局、政府、つまり他人にすべてを期待するのではなく、一人一人がどう生きていくかを選択することなのであろう。現実を受け入れ、たくましく生きていくしかないのだ。ハンター・ケネディーが言うように、人々があらゆる恐れから解放されて生きることができるようになったとき、初めて本当の"フリーダム"が訪れるのだろう。そうなったとき、南アフリカは本当の意味で世界一の国になるのである。